住まいのお金
やってはいけない節約術|家づくりでコストカットしすぎた人の後悔

建てる前は正解だと思っていた。
でも、暮らして気づいた“落とし穴”
マイホームを建てるとき、誰もが「できるだけ予算を抑えたい」と考えます。
ですが、“節約”と“妥協”を混同してしまうと、入居後に後悔することになるのが家づくりの怖いところ。
「予算を削った部分が暮らしに支障をきたした」
「結果的に、後から直すのに余計な費用がかかった」
そんな声は、私たち住宅会社にも少なくありません。
この記事では、家づくりの現場でよく見られる“やってはいけない節約術”と、
後悔しないための考え方・代替案を解説します。
1. 「断熱性能」を削る節約は“見えない損失”になる

一見すると“設備”や“素材”のグレードを落とすだけに見える断熱材。
しかし実際は、家の性能と快適性の根幹を支える重要な要素です。
〈❌ やってはいけない節約例〉
「高性能断熱材にすると100万円ほどアップと言われたので、安いものに変更しました」
この判断、入居後にこうした声につながります。
「冬の朝、部屋が冷え切っている」
「冷暖房費が思った以上に高い」
断熱性能が低いと、室温を一定に保つためにエアコンがフル稼働。
10年単位で見ると光熱費が100万円以上の差になることもあります。
さらに、家の温度差が大きいと結露やカビの発生、ヒートショックのリスクも上昇します。
〈💡 節約のポイント〉
断熱材のグレードを下げるより、
・不要なオプション設備を減らす
・外構を後回しにして建物性能を優先する
といった「後から変えられる部分を削る」ほうが合理的です。
2.「構造・耐震性能」を最低限にするのは危険

最近は「耐震等級3」が標準仕様になりつつありますが、まだ一部ではコストを抑えるために耐震性能を下げる選択をする方も。
しかし、地震や台風などの自然災害が増えている今、命を守る部分に節約は禁物です。
〈❌ やってはいけない節約例〉
「等級2でも建築基準法はクリアしているから大丈夫だと思った」
実際の災害時、建築基準法レベルの家が「倒壊まではしなくても、住めないほどの損傷」を受けるケースがあります。
つまり、修繕や建て替えの費用が“節約分を超えて”発生する可能性があるのです。
〈💡 節約のポイント〉
構造や耐震、基礎部分は「あとから強化できない」分野。
ここはしっかり投資しておくことが、長期的に見ると一番の節約です。
3.「収納スペース」を削ると、暮らしが雑然とする

「収納を減らして建築面積を小さくすればコストダウンできる」と思いがちですが、
収納が足りない家は日常的なストレスにつながります。
〈❌ よくある失敗〉
「子ども部屋を広くしたかったので、クローゼットを省いた」
「洗面室の収納棚を後で買えばいいと思った」
結果として、生活が始まると——
「片づかない」「掃除が面倒」「見た目が雑然としている」と感じることに。
後から収納家具を買い足すと、合計金額は造作収納より高くなることもあります。
〈💡 節約のポイント〉
収納は「量」より「配置」。
・家族構成や暮らし方をもとに必要量を割り出す
・ウォークインをやめて可動棚+扉付き収納にする
など、“機能を落とさずコストを下げる”工夫がおすすめです。
4. 「照明・コンセント・スイッチ」を軽視する

打合せ終盤で「細かい部分はお任せします」となりがちな照明計画。
しかし、ここを軽視すると毎日の生活の不便さに直結します。
〈❌ よくある後悔〉
・リビングの照明が眩しすぎて落ち着かない
・キッチン裏のコンセントが足りない
・廊下が暗い
・寝室で照明を消すために立ち上がる
照明・電気工事の追加は入居後だと数万円単位の追加費用が発生します。
〈💡 節約のポイント〉
・明るさを求める場所と、雰囲気を重視する場所を分ける
・調光スイッチを設けて、照度を自由に調整できるようにする
・コンセントは“少し多いくらいでちょうどいい”
照明計画は、生活動線の“快適性”を左右する大切な要素です。
5. 「外構工事」を後回しにして生活動線が悪化

「外構は入居してからゆっくり考える」という方も多いですが、
駐車場やアプローチが未完成のままだと、生活の利便性や安全性に影響します。
〈❌ よくある失敗〉
「雨の日に玄関までの動線が泥だらけになる」
「駐車スペースが狭くて出入りが大変」
「外からの視線が気になる」
これらは入居後に改善しようとすると、再施工で割高になるケースがほとんど。
〈💡 節約のポイント〉
・フェンスや植栽など“装飾”部分を後回しにして、駐車スペースやアプローチなど“生活の基盤”部分を優先施工する
最低限の外構計画は、建物と同時に考えるのが鉄則です。
6.「標準仕様の確認」をせず、価格だけで比較する
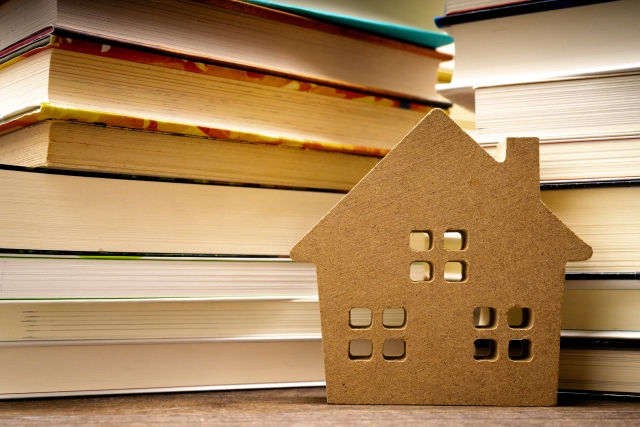
他社より見積もりが安い!と思っても、標準仕様の中身が違うことはよくあります。
たとえば
・サッシがアルミ樹脂か、樹脂サッシか
・外壁材のグレード
・照明・カーテンの有無
こうした“見えにくい差”が後から費用増につながります。
〈💡 節約のポイント〉
「見積りの金額」ではなく、「同じ条件で比較する」こと。
住宅会社に「標準仕様リスト」や「仕様書」を提示してもらい、どこまでが含まれているのかを確認しましょう。
7. 「担当者に相談せず、自己判断で削る」

最近はSNSやYouTubeで“節約術”が多く紹介されています。
しかし、それを自分の家にそのまま当てはめるのは危険です。
家の構造・地域の気候・家族構成が違えば、正解も変わります。
〈❌ よくある後悔〉
「ネットの情報を参考にしたけど、自分の家には合わなかった」
節約のつもりが、後からリフォーム費用が発生して結果的に高くつくパターンです。
〈💡 節約のポイント〉
担当者に「削る部分と削ってはいけない部分」を相談しましょう。
プロは多数の実例を見ているため、“費用対効果の高い節約”を一緒に考えてくれます。
8. 後悔しない家づくりのための心得

1.短期的な節約より、長期的なコストを意識する
▷ 光熱費・メンテナンス費まで含めた“生涯コスト”で考える。
2.優先順位を決めて、削る部分を明確にする
▷ 性能>構造>間取り>設備>外構 の順で検討。
3.「今」より「10年後の暮らし」を想像する
▷ 子どもの成長や親の介護など、ライフステージの変化も考慮
この記事のまとめ
- 節約の目的は「安くすること」ではなく、「ムダを減らすこと」
- 本当に必要なものを見極めて、将来まで快適に暮らせる家づくりを目指しましょう
































